| Home | |||
| Part10�@2015�@(11) | 11�� | ||
| �P�@2�@3�@4�@5�@6�@7�@8�@9�@10 �@11 12 | |||
���̂��ώ@��A�l�I�ȎU��ŏo������
�l�G�܁X�̉ԁA���̂��E�E�E�ʐ^�ƎG���ł�
����ɁA���[�����O���X�g�ł������������Ԃ̃��[���̈ꕔ��]�ڂ��Ă��܂�
�@---�@�a�̎R�ɂ��Z����As�����[�������������܂��� �u�@�������A�܂��A���̂�������܂����B ����A�����T�L�V���W���Ȃ��āA�I�E�M�^�P�A�A�~�^�P�����铙�B�ςȋG�߂ł���B
1 �C�k�Z���{���^�P�c�ہc�P�͗��`�ŏ������F���ۂ��B���͔��זт�ттĂ���悤���B 2 �I�E�M�^�P-1�c�P�͐R�l�`�A�S���������B���̎P�̐F�������B 3 �I�E�M�^�P-2�c�Ђ��͂��a�Ő��������A���R�̑��`�Ɍ������B 4 �`�V�I�^�P�c�P�̐^�������Ԃ��A���ӕ��͔����B�P�̕��ˏ�̏���A���̋�����̃t�����W�A�Ƃ����������B 5 �j�K�N���^�P�c�����̋r���̙z�Ƃ����p�ɍ��ꍞ�ށB 6 �t�^�g�Q�z�R���^�P?1�c���t�y��ɎU���A�a4-5cm�B�ł����B���قł���B 7 �t�^�g�Q�z�R���^�P?2�c��̎h������悤�Ɏv���̂����c 8 �t���m�X�M�J���^�P�i�؉��́j�c�X�M�͖̌؏�ɌQ���A���̂Ђ��������B�v �@�E�E�E�@�J�����Ȃ�10���A�C���̍���11���B�g�t�����߂Ă��܂悤���A�ǂ�����N�ɔ�ׂ�ƃC�}�C�`�B�L�m�R����N�ɔ�וςȊ����B����ł��A�R���X�^���g�ɃL�m�R�������o���BAs����̍s���͂ɂ͓���������܂��isimo�j�B |
 |
 |
|
| �P | 2 | |
 |
 |
|
| 3 | 4 | |
 |
 |
|
| 5 | 6 | |
 |
 |
|
| 7 | 8 |
�y�[�W�g�b�v�w
| �@ �@�g�t�����߂Ċ���Ó���T�����A��͂荡�N�̍g�t�͊��ҊO��B���������܂�܂łɒ��͂ꂵ�A�ނ�A���ɔ���ꂽ�t�������A�c���Ă���t�͗̂܂܂ȂǂȂǁE�E�E�B�@�����_�Ђ̃I�I���~�W�H�������͗t�����ł��܂��Ă���Ƃ����̂ɁA�c�����t�̐F�Â��͗�N�ɔ�ׂ�ƃC�}�C�`�B �@�g�t����ߒ��߂����̎U�����ցB8���Ƀi���͂�̃R�i������{����Ή������肢���Ă����߂��y�L�̋u�ł́A���̌㒲�ׂĂ�������\�{�قǂ̃i���͂�̎��|�A�r�j�[�������Ȃǂ̏��������Ă��������Ă���B����ŏ��Ȃ��Ƃ��A��������i���͂ꂪ�g�U����邱�Ƃ͂Ȃ��悤�ł��B �@�g�t���l�L�m�R���������ُ̈�ȋC��Ɍ˘f���Ă���̂ł��傤���H�u���̐H�p���̂���葁���i���H�Ɂj��������v�͂��̃n�c�^�P�����~�̍����A���������H�ɔ������邱�Ƃ̑����R�����T�L�V���W�̌Q�������������邽�B |
 |
 |
|
| ����Ó��̍����_�Ђ̃I�I���~�W�ł��傤���H�@���̖͔����قǂ͗t�������Ă��邪�@���̖ł͗̃��~�W������ | ||
 |
 |
|
| �߂��y�L�̋u�̃i���͂�@���|�A�r�j�[���핢����Ă��� ����ŁA���Ȃ��Ƃ��������k���n�Ƃ��ăi���͂ꂪ�L���邱�Ƃ͂Ȃ����� |
||
 |
 |
|
| �Z�������E�A�}�������E�ɑ��� �P�O���Ƃ��Ă��@���u�R�E�W�@����Ó� |
�P���Ƃ��Ă��A���h�I�V�Ɏ��Ă��� �c���A���h�I�V�@�߂��y�L�̋u |
|
 |
 |
|
| ���H�Ɍ������邱�Ƃ̑����n�c�^�P�����@���~���@ | ||
 |
 |
|
| ��������@���H�ɂ悭��������@�R�����T�L�V���W�@ | ||
 |
 |
|
| �k�����C�O�` | �V���Q�J���^�P | |
�y�[�W�g�b�v�w
| �@ �@�����O�����C�Ɋ����Ȃ�G�߂������ɐi�悤�ł��B����R�[��������L�m�R���~�����肩�H�قƂ�ǎp�������Ȃ��B����n���ɉf����^�J�m�c���A�R�V�A�u���̉��t�Ɏv�킸���Ƃ�Ă��܂��B������̌������G�ߕ��Ńi���͂�Ō͎������R�i���̂P�O�����قǂ̎}�������Ă���B�я��ł̓t���C�`�S�̐Ԃ��������B�@ �@�����͂�̃R�i���̊��ɂ������k�����c�o�^�P�������邪�����G�ߕ��Ɋ������Ă���B�R�i���̗����}�̃V���L�N���Q�͍������������p���B���J�����Ō���ꂽ�j�K�N���^�P�̗c�ۂ������B�A���Q�R�x�j�`�������^�P�A�����T�L�S���^�P���L�m�R�̏��Ȃ��Ƃ��ɂ͗ǂ���ʑ̂ɂȂ��Ă����B |
 |
 |
|
| �^�J�m�c���@���t | �R�V�A�u���@���t | |
 |
 |
|
| �t���C�`�S | �R�i���@�����͂�̎��̎}�� �a�V�|�W�����̂Ƃ���Ő܂�ė������Ă��� |
|
 |
 |
|
| �R�i���͎��@�����C���̃k�����c�o�^�P�@ | ||
 |
 |
|
| �V���L�N���Q | �j�K�N���^�P | |
 |
 |
|
| �A���Q�R�x�j�`�������^�P | �����T�L�S���^�P | |
�y�[�W�g�b�v�w
 �@ �@�@��͓��̎U�����̍����̂��̂� �@�@�Y��ȃk�����X�M�^�P���h�L�����o�}�� �@���̂Ƃ���J����������~�����Ɠ�͓��̎U�������L�m�R�����₩�ɁB �@�v���Ԃ�ɐH�ׂ���H������H�̃k�����X�M�^�P���h�L���o�}���Ă����B �@������������V���L�c�l�m�T�J�Y�L�߉�������ɂȂ�T���ƁA���b�L�[�Ȃ��ƂɈ�����c���Ă����B �@�̂̃}�c�^�P�R�����͂ꂪ�����������c���������قƂ�Ǘ\�h�ڎ�H���Ă���B���a�P�O��������Ə��͂�Ō͂�Ă��邪�A������ׂ����̂����Ƃ��������тĂ���B �@���Ăɂ����ɕ����Ă���ƁA�����A�~�^�P����{�������B�����T���ƁA�ׂ����̐����c��ɗ{���Ă�����Ă���A�~�^�P�A�I�E�M�^�P�A�k�����C�O�`�����������撣���Ă���B �@���̂ق��v���Ԃ�ɏo�������C�^�`�^�P�A�E�X�x�j�C�^�`�^�P�̑傫�ȌQ�������������Ƃ��Ė��͓I���B �@����̉J�ɐo���ꂽ�c�`�O���������������B�K�i�̏R�㕔���ɐ����鏬���ȃA���m�^�C�}�c���������Ȃ���Ԃ��F�Ŗڗ��B ���@2020.06.08�@�V���L�c�l�m�T�J�Y�L�߉���Ƃ������̂́A��O�@�V�����ɂ����{�V�Y��e���K�C�L�c�l�m�T�J�Y�L�Ƃē��{�ۊw����2020.5�ŕ��ꂽ���́B |
 |
 |
|
| �я��̃Q���m�V���E�R | �k�����X�M�^�P���h�L | |
 |
 |
|
| �k�����X�M�^�P���h�L | �e���K�C�L�c�l�m�T�J�Y�L |
|
 |
 |
|
| �A�~�^�P | �I�E�M�^�P | |
 |
 |
|
| �I�E�M�^�P�ƃA�~�^�P�͐}�Ӓʂ蒇�ǂ� | �k�����C�O�` | |
 |
 |
|
| �C�^�`�^�P�̌Q�� | �E�X�x�j�C�^�`�^�P�̌Q�� | |
 |
 |
|
| �A���m�^�C�}�c | �c�`�O�� |
�y�[�W�g�b�v�w
�@Ym����̃��[���ɃW�b�Ƃ��ċ����Ȃ��Đ���w�ŁBYm���s���ꂽ�����x�X�g�^�C�~���O�������悤�ŁA�����͊G�ɂȂ�k�����c�o�^�P�͂R�{�����B �@������߂��ɁA�����Ă݂���̂ł��ˁB���b�L�[�Ȃ��ƂɁA����R�ł͏��߂ăi���^�P�ɏo�����܂����B�@ �@�i���͂�̖X�̕����͐��������B�����͂ꂵ������̖��n�J�����^�P�Ȃǂɕ����Ă���B�����ȏ�Ɍ͂�͗��ċۂɑ����R�͂�����Ă���̂ł��傤�ˁB����ł̓i���͂�̎��͖w�Ǖ��u����Ă���B���ꂾ������Ă���Ƒ傫�Ȏ}�̗����̊댯�������������ӊ��N�̌f�����Ȃ��B �@���������͂�}�ł́A���̔������J�~�E���R�^�P�A�����̃V���L�N���Q�A�N���R�u�^�Ȃǂ�������̃L�m�R�����������ē��₩���B �ƂɋA��m�F����ƁA�����̃L�m�R�́A�i���R�̔�������͕s�������A����ȊO�͂��ׂăi���͂�̃R�i���̗����|�A���}���甭���������̂��B |
 |
 |
|
| �V���n�J�����^�P�Ƌ��� ���������͌������@�k�����c�o�^�P |
�G�ɂȂ���̂́@���̂R���H���R�̂̂� �����̃k�����c�o�^�P |
|
 |
 |
|
| ����R�ł͎��͏��Ζʂ̃i���R | ||
 |
 |
|
| ����R�ł͎��͏��Ζʂ̃i���R�@�E�q�����܂Ł@���炭���a�� | ||
 |
 |
|
| ���͑傫�ȃV�C�m�L�@�E�̓R�i�� ����̃i���͂�́@�قƂ�Ǖ��u����Ă��� |
��c�u�˂̎q�ǂ��̐X�@�i���͂�̃R�i�� ���Ȃ蔰�|����Ă��邪 �@�������̏����͂���Ă��Ȃ��悤�� |
|
 |
 |
|
| �я��ŔӏH������������@�X�Y���E���̎� | �i���͂�̗����@�n�J�����^�P | |
 |
 |
|
| �i���͂�̗����@�j�N�E�X�o�^�P | �i���͂�̗����@�T�K���n���^�P�@ | |
 |
 |
|
| �i���͂�̗��� ���P�C���^�P | ||
 |
 |
|
| �i���͂�̗��ɂā@�E���x�j�K�T | �i���͂�̗��ɂā@�q���X�M�^�P | |
 |
 |
|
| �i���͂�̗��������}�ł́@�J�~�E���R�^�P | �i���͂�̗��������}�ł́@�V���L�N���Q | |
 |
 |
|
| �i���͂�̗��������}�ł́@�N���R�u�^�P | �i���͂�̓|�A���ő����݂�ꂽ �@�n�i�r���j�J���^�P�@ |
|
�y�[�W�g�b�v�w
�@---�@�����s�ɂ��Z����Ym�����[�������������܂����i11/17�j �u�@�O���đO�X��̉J�̌�A�i���͂�̃R�i���ɂ��̃k�����c�o�^�P�������������Ă��܂����B ���������̂قƂ�ǂ���̓͂��Ȃ������Ƃ���A��{���̃R���f�W�ł͂Ȃ��Ȃ�����B
�ł��K���Ȃ��ƂɈ�{�͒Ⴂ�ʒu�A��{�͎��L���ĉ��Ƃ��A�Ƃ������Ƃŏ�����܂����B
�P�P���ƂP�V���̎ʐ^�̈ꕔ�ł��B
�J�G���^�P�A�n�i�r���j�J���^�P�����ăk�����c�o�^�P�A���́H�y���݂ł��ˁB�v
�@�E�E�E�@�ޗǎs��In����u�k�����c�o�^�P�����ł��ˁB�k�����c�o�^�P���ɏ��҂��Ē����܂��B �@�E�E�E�@�P�O���ُ͈�ȏ��J�B�����ĂP�P���ُ͈�ȉ������ƉJ�̑����B���̂������H�ґ�Ȍi�F�ł��ˁB���ꂾ���������P�����ԂƊO�ɃL�m�R���Ȃ��Ă��[�������ł��܂��ˁisimo�j |
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
�y�[�W�g�b�v�w
 ---�@�ޗǎs�ɂ��Z����In�����[�������������܂��� �u����̔[��ł͔����������̂���ŐH�߂��܂����B�����A���g�쑺���H�x�Ƀo���G�[�V�������[�g�Œ��o���āA���̌㖾�_�������Ă���ʏ탋�[�g�ʼn��R���܂����B���悻�W���U�O�O�b�t�߂̒��ԏ�߂��̒n�ʂ����^�̉��F�|�������x�[�W���F�̃L�m�R�����������Ă��܂����B�Q�O�p���炢�̑傫����?�@��܂Ŕ��f���Ă݂ĉ������B����ł͕��i�����������Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂����B�c�o������A�q�_���Y��Ȕ����O���[�ł����B�����ƔS��������ׂ��ׂ��Ǝ�ɂ��܂����B�͂��n���ɂ������ꂽ�Ȃǖ����悤�ȂƂ���ł��B����͉��ł��傤��? �B�v �@�E�E�E�@�L�i�R���܂Ԃ����悤�Ȋ����ł͂Ȃ������ł����H�R�K�l�^�P�ł����Ǝv���܂��B�t����Ђ̕t�߂̐X�ŕS�{�ł͂����Ȃ����炢�̑傫�ȌQ�����������Ƃ�����܂��B�R�k�̃t�B�[���h�u�b�N�X�ł́u�H�A�ݒ��n�̒��ł��N�����n������v�̂悤�ł��B �H�ׂ܂������ǁA���G�肪�ǂ������L�m�R���Ǝv���܂��B���Ȃ��Ƃ��i�{�[�������ɂ��������ł͂Ȃ������ł��B�ق��������Ђ́u�R�̂�L�m�R�̂����v�i���R���� 1998�N�j�ł́u����������ǂ��v�V�Ղ���u�ߕ��A�畨�A�ѕ��ɂ������Ă���ƋL�ڂ�����܂��B�isimo�j�B |
 |
 |
|
�y�[�W�g�b�v�w
�@---�@�a�̎R�ɂ��Z����As�����[�������������܂��� �u�@�J���~��A�����������̂����łĂ����悤�ł��B 1�@�I�E�M�^�P1�c�͂��߃x�j�^�P���H�Ǝv�����̂ł����A�P�ɔS������A���炩�ɈقȂ�B
2�@�I�E�M�^�P2�c���́u�Ђ��v���������B���ɐG���Ƃ�≩�ς��܂����B 3�@�L�q���^�P1�c���Ă��邾���ł����Ƃ�B 4�@�L�q���^�P2�c�L�q���^�P1�Ƃ͈Ⴄ�\��B 5�@�V���^�P�c�P�̗��̃V���V�����V���^�P�炵���B 6�@�j�K�N���^�P�c�j�K�N���^�P�̂����܂����ɂ�����������B 7�@�q���^�P1�c�ړI�̃q���^�P�ɂ����ċ����C���B 8�@�q���^�P2�c�����ԕa�łȂ��Ă悩�����B�v �@�E�E�E�@�������q���^�P�ł悩�����ł��ˁB�����q���^�P�������̂ł����A���������R�u�a�ɐN����Ă��ĔߎS�Ȃ��̂ł����B�L�q���^�P�̗c�ۂ͂����Ă��E�b�g���Ƃ��閣�͂�����܂��ˁisimo�j�B |
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
�y�[�W�g�b�v�w
�@�������������P�}�[�N�����Ă���BYm����̑f���炵���ʐ^�Ɏh�����āA�_�����Ŋ������ʂ��U��B���Ƃ��J�ɂ͍~��ꂸ�ɉƘH�ɂ����Ƃ��ł����B �@�����̓x�j�q�_�^�P�f�[�H����������Ƃ���ʼn��J�����������x�j�q�_�^�P�ɏo�������B �@���ړ��ẴG�m�L�^�P�͐芔�A�|����������P������Ă��܂��Ă���B�c�����芔�̓G�m�L�^�P�ɐH�ׂ����ꂽ�悤�Ő������낭�Ȃ�A�n�J�����^�P�Ȃǂɕ����Ă���B�����ȃG�m�L�^�P������ł��邪��������悭�Ȃ��悤�ő����������̂��̂������B |
 |
 |
|
| �芔�ɍs��@�x�j�q�_�^�P | �c�ۂ������@�x�j�q�_�^�P | |
 |
 |
|
| �[���Ȏp�@�x�j�q�_�^�P | �c�ۂ����@�G�m�L�^�P | |
 |
 |
|
| �n�_�C���K�T | �����T�L�V���W |
�y�[�W�g�b�v�w
�@---�@�����s�ɂ��Z����Ym�����[�������������܂��� �u�@�Q�O�O�R�N�P�P���P�R���A���̂��̂����킩�炸�t�B�����J�����������Ă��낤�낵�Ă����Ƃ��ɎB���Ă��������̂ɐ���ĉ�i�����s�j�B �V���L�c�l�m�T�J�Y�L�i�������O�A���肷���j�V���L�c�l�m�T�J�Y�L���h�L�A��������t���珉�Ăł�������A���̗����t�߂ł�������
�悭�킩��Ȃ���������ł��Ȃ��B
�@S�����g�o���߉���Ƃ���Ă����̂͑Ó������A���������ꂢ�Ȏʐ^�͂����܂����B�@�ĉ�͂��ꂢ�Ȍő̂ł͂Ȃ������̂ł�������Ɍ��C�Ă�������T���Ȃ��ẮB�S���ڂ͂Q�O�O�R�N�łł��B�v
�@�E�E�E�[�����͓I�ł��B�����ꂾ���ł������ɍs���l�ł�������悤�Ɏv���܂��isimo�j |
 |
 |
|
 |
 |
|
�y�[�W�g�b�v�w
 �@�@"�J�S�^�P�ł��傤��" �@---���s�ɂ��Z����G�����[�������������܂��� �u�@����ʐ^�̃L�m�R�������܂����@�J�S�^�P�ł��傤�� �@���������߂���ƒ��ɔ]�݂��̂悤�Ȃ��̂������Ă���A �@������o���ĐG���Ă���Ƃ���J���ĖԂ̂悤�ɂȂ�܂����v �u�@�䏊�s�́E�E�E�Ō����܂����@�y�ɐ����Ă܂��� �@�Ђ���̕����͒����ʼn����Ɠ����̔S�t���o�Ă��āA�����Â����������ł� �@�X�Y���o�`�͂��̔S�t���z���ɗ���̂ł��傤���H �@������܂������݂�Ȃ܂����̏�Ԃ������̂��c�O�ł��v �@�E�E�E���ۂł��ˁB�ȑO�A��̒��ŃS�\�S�\�Ɠ����o���r�b�N���������Ƃ�����܂��B�isimo�j |
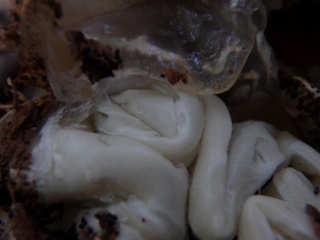 |
 |
|
�y�[�W�g�b�v�w
�@�_�˂̋ۗFK����A������Is�v�ȁASat����Ƌ��ɐ_�˕��ʂ̎R�ցB�P�O���͗��j�I�ȏ��J�̂��߁A���̋G�߂��z���V���W�Ȃǂɂ͈�ԂƂ��������������R�̓J���J���B �@����ł��A�R��m��s�����ē��̂����ŁA�o�n�߂̃z���V���W�A�V���t���V���W�A�����������������}�c�^�P���قƂ�ǒɂ݂��Ȃ��f���炵�����肾�B�̊O�Ŗڂɂ����̂̓q���J�������^�P���炢�B |
 |
 |
|
| �z���V���W | �z���V���W | |
 |
 |
|
| �z���V���W | �z���V���W | |
 |
 |
|
| �V���t���V���W | �V���t���V���W | |
 |
 |
|
| �}�c�^�P | �q���J�������^�P |
�y�[�W�g�b�v�w
| Part10�@2015�@(11) | 11�� | ||
| �P�@2�@3�@4�@5�@6�@7�@8�@9�@10 �@11 12 | |||
�y�[�W�g�b�v�w